当研究員の八重樫が、8月23–24日に大阪国際会議場(グランキューブ大阪)で開催された日本認知・行動療法学会 第51回大会において、自主企画シンポジウム「認知行動療法を社会に届けるためのキャリアパス:多様なフィールドにおける研究と実践の最前線」に指定討論として登壇しました。
研究を現場へ、現場の知見を研究へ
CBT(認知行動療法)は、こころの悩みや行動上の困りごとを「考え方(認知)」と「日々の行動」を少しずつ整えることで軽くしていく“やり方”です。
一方で、研究では効果が確かめられていますが、「研究で良いと分かったことが、そのまま現場で続けられるとは限らない」という課題(エビデンス・プラクティスギャップ)があります。
このシンポジウムは、そのギャップを小さくするために、大学や研究機関だけでなく、医療・福祉・産業など幅広い現場での研究と実践の重要性を共有し、具体的な事例と議論を通じて社会実装をどう進めるかを考える場として企画されました。
現場とエビデンスの「あいだ」をつなぐ
各発表の共通点・相違点を踏まえ、研究知と実践知をどのように社会へ届けるかという観点から、八重樫は次の点を共有してきました。
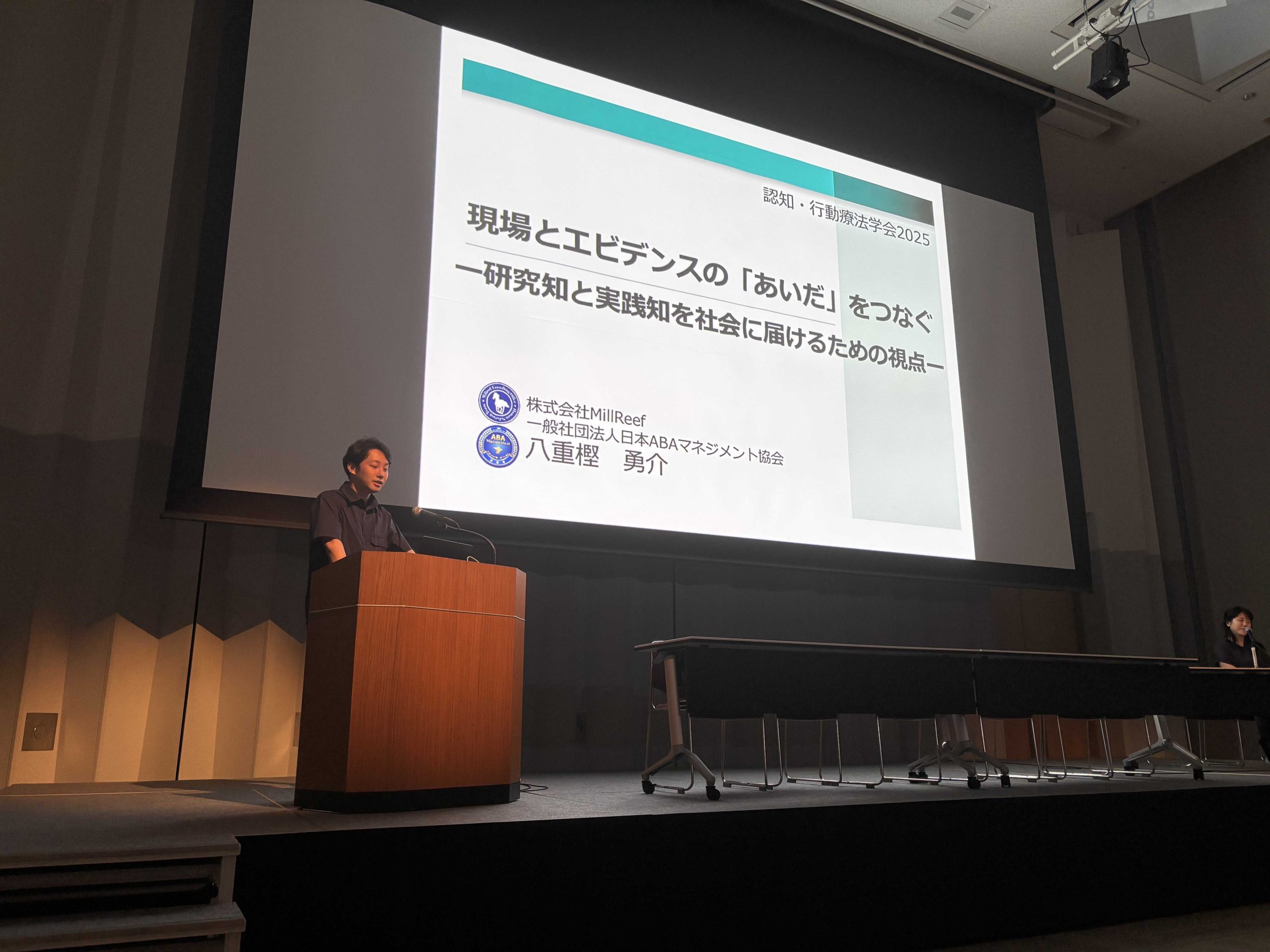
1) 社会実装で重視していること
-
行動データに基づく問題解決:応用行動分析学(ABA)を、研究サービスとしてではなくコンサルティングのサービスとして活用し、組織のパフォーマンス向上・人材育成・コミュニケーション改善に結びつける実務。
-
現場で続く形への落とし込み:研究成果を、現場の手順・指標・運用に接続して定着を図る。
2) 実践上の工夫と葛藤
-
行動と成果の両立:行動だけの変化では受け入れられにくい局面があり、行動と成果の双方を標的に置く必要性。
-
“創造的業務”への適用の難しさ:単純な量的指標より、デザイン・開発など唯一性や創造性が高い仕事での適用は設計が難しいこと。
-
総合的なパフォーマンス・マネジメント(PM)視点:個々の行動に入る前に、他の成果・行動指標との相互作用も含めた組織全体のシステムを分析する重要性。
-
国内普及の障壁の整理:日本における組織行動マネジメント(OBM)実践の少なさ、文化・役割の違い、長期的に標的行動を維持しにくい現場状況など。
本シンポジウムは、研究と現場が往復することで初めて“続けられる改善”が生まれること、そして多様な立場の実践が研究の社会実装を前に進めることを改めて示しました。
日本ABAマネジメント協会では、本議論で得られた示唆を今後の研修・制度運用支援に反映し、現場とエビデンスの「あいだ」を近づけてまいります。ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
